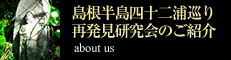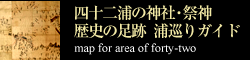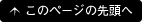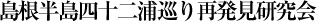瀬崎浦
| 浦名 | 瀬崎浦(せざきうら) |
|---|---|
| 神社名 | 日御碕神社 |
| 祭神 | 都久津美神 |
| 所在地 | 松江市島根町野波3776 |
瀬崎日御崎神社
神風(かみかぜ)によする 瀬崎(せざき)の波(なみ)の花(はな)を
そそげば清(きよ)き我(わが)心(こころ)哉(かな)

ただいま準備中です

瀬崎の日御碕神社では、平成二七年の遷宮を控えて、この十月に仮遷宮が行われ、境内での湯立ての神事、三年ぶりの夜神楽も催されました。夜神楽は、「悪魔切り」等の演目もあり、誕生した子の幸福を祈念して紅白の餅やお菓子が集まった沢山の人々に撒かれました。実に元気の出る夜神楽でした。
瀬崎は、出雲国風土記にある「瀬崎の戍」の地です。神社を登り切り、鳥居で振り返ると「瀬崎の戍」があったと伝わる山が見えます。この山の左方向には、天空の岬のキャッチフレーズの宿泊施設「マリンバーク多古鼻」があり、ここが島根半島の最北端となり、晴れていれば隠岐の島を見はるかす絶景の岬です。
瀬崎のの平山は、北側には隠岐諸島が正面にあり、東側に千酌・北浦方面、東南方向に鳥取県大山の視界が開けていて、日本海の見張り・周辺への連絡などには、とても有利な場所だったと思われます。平山の登山口付近の進入路あたり、梶野工務店の看板を下った辺りには、戍人(まもりびと)
を祀った地区内各所にあった五輪塔が12基まとめられています。五輪塔は県道から瀬崎集落に入ってすぐのところにも7基ばかりあります。古来伝わる「瀬崎の戍」伝承の証です。
建武の新政で知られる後醍醐天皇が隠岐の島から逃れてきて上陸したのも、ここ瀬崎で、今でも「綱掛けの松」が守られ、様々な説話が残っています。
また、明治の廃仏毀釈運動により、隠岐の島から仏像が避難されたと今に伝わり、庵寺に五体あります。修復を重ねて、かなり傷んでいますが、鎌倉時代の雰囲気が一部残っているものもあると聞きました。
瀬崎では三月一日に一年の無事を感謝し、五穀豊穣・大漁等を祈願する恵比寿祭りが行われます。こうして各地域の祭礼の趣旨を見ると、一月一日が一年の切り目ではなくて、様々な理由で祈りの時期が設定されていることが分かりました。

『雲陽誌』には「爾佐明神 瀬崎といふ所にあり都久豆美命なり」と見えており

瀬崎漁港近くの裏山、民家の間を縫いながら境内に上るが立地的に大変分かりにくい神社である。地元の故・小野啓二郎氏の記録によれば昭和三十七(一九六二)年まで境内に幹回り十メートルに及ぶ老松があったという。神社の目印だったのであろう。
この瀬崎の日御碕神社は古代の神社を考える上で極めて重要な情報を内含しているようである。享保年間の『雲陽誌』には「爾佐明神 瀬崎といふ所にあり都久豆美命なり」と見えており、祭神・社名とも現在千酌に鎮座している『出雲国風土記』島根郡条にみえる爾佐神社と全く同じである。社伝では往古千酌の爾佐神社を勧請し、宝永年間に日御碕神社を合祭したという。
問題は古代の「千酌駅家」の「千酌」の名を冠した神社が千酌地域にない点である。『出雲国風土記』島根郡条では実に十社が脱落している事実がある。可能性として「千酌社」があったとすればそれは千酌にあり、この日御碕神社が「爾佐」神社であったとしても不思議ではないのである。
御祭神の「都久津美命」であるが記紀にはみえず、『出雲国風土記』島根郡千酌駅家条に「伊佐奈枳命の御子」とみえている。一説に月読命ではないかとされている。

| 浦名 | 瀬崎浦(せざきうら) |
|---|---|
| 神社名 | 日御碕神社 |
| 祭神 | 都久津美神 |
| 所在地 | 松江市島根町野波3776 |
瀬崎日御崎神社
神風(かみかぜ)によする 瀬崎(せざき)の波(なみ)の花(はな)を
そそげば清(きよ)き我(わが)心(こころ)哉(かな)
瀬崎の日御碕神社では、平成二七年の遷宮を控えて、この十月に仮遷宮が行われ、境内での湯立ての神事、三年ぶりの夜神楽も催されました。夜神楽は、「悪魔切り」等の演目もあり、誕生した子の幸福を祈念して紅白の餅やお菓子が集まった沢山の人々に撒かれました。実に元気の出る夜神楽でした。
瀬崎は、出雲国風土記にある「瀬崎の戍」の地です。神社を登り切り、鳥居で振り返ると「瀬崎の戍」があったと伝わる山が見えます。この山の左方向には、天空の岬のキャッチフレーズの宿泊施設「マリンバーク多古鼻」があり、ここが島根半島の最北端となり、晴れていれば隠岐の島を見はるかす絶景の岬です。
瀬崎のの平山は、北側には隠岐諸島が正面にあり、東側に千酌・北浦方面、東南方向に鳥取県大山の視界が開けていて、日本海の見張り・周辺への連絡などには、とても有利な場所だったと思われます。平山の登山口付近の進入路あたり、梶野工務店の看板を下った辺りには、戍人(まもりびと)
を祀った地区内各所にあった五輪塔が12基まとめられています。五輪塔は県道から瀬崎集落に入ってすぐのところにも7基ばかりあります。古来伝わる「瀬崎の戍」伝承の証です。
建武の新政で知られる後醍醐天皇が隠岐の島から逃れてきて上陸したのも、ここ瀬崎で、今でも「綱掛けの松」が守られ、様々な説話が残っています。
また、明治の廃仏毀釈運動により、隠岐の島から仏像が避難されたと今に伝わり、庵寺に五体あります。修復を重ねて、かなり傷んでいますが、鎌倉時代の雰囲気が一部残っているものもあると聞きました。
瀬崎では三月一日に一年の無事を感謝し、五穀豊穣・大漁等を祈願する恵比寿祭りが行われます。こうして各地域の祭礼の趣旨を見ると、一月一日が一年の切り目ではなくて、様々な理由で祈りの時期が設定されていることが分かりました。
『雲陽誌』には「爾佐明神 瀬崎といふ所にあり都久豆美命なり」と見えており
瀬崎漁港近くの裏山、民家の間を縫いながら境内に上るが立地的に大変分かりにくい神社である。地元の故・小野啓二郎氏の記録によれば昭和三十七(一九六二)年まで境内に幹回り十メートルに及ぶ老松があったという。神社の目印だったのであろう。
この瀬崎の日御碕神社は古代の神社を考える上で極めて重要な情報を内含しているようである。享保年間の『雲陽誌』には「爾佐明神 瀬崎といふ所にあり都久豆美命なり」と見えており、祭神・社名とも現在千酌に鎮座している『出雲国風土記』島根郡条にみえる爾佐神社と全く同じである。社伝では往古千酌の爾佐神社を勧請し、宝永年間に日御碕神社を合祭したという。
問題は古代の「千酌駅家」の「千酌」の名を冠した神社が千酌地域にない点である。『出雲国風土記』島根郡条では実に十社が脱落している事実がある。可能性として「千酌社」があったとすればそれは千酌にあり、この日御碕神社が「爾佐」神社であったとしても不思議ではないのである。
御祭神の「都久津美命」であるが記紀にはみえず、『出雲国風土記』島根郡千酌駅家条に「伊佐奈枳命の御子」とみえている。一説に月読命ではないかとされている。